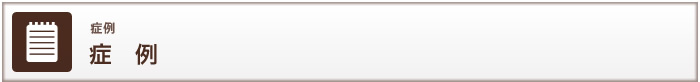
昨年10月に「一過性の意識障害」が主訴で来院された30代女性の症例です。
【症状】
約1年前夏頃から1年の間に突然意識が無くなり外出先で倒れる事7回(数時間意識が戻らず)。加えて、月経前に帰宅直後、玄関先で意識を失う事が毎月のように起こり、月経中(特に一日目)は外出先で意識が無くなる。
【随伴症状】
・立ちくらみ、フワフワとした眩暈(地に足がついていない感じ)と動悸。
・食欲減退、嘔気(嘔吐なし)
・後頚部の張りがひどく首の回旋不可(左右共)。
・便秘と軟便を繰り返し、排便後栄養が全部出る感じがして疲労感が増す。(以前は便秘傾向)
・往復40分の徒歩通勤で疲労感。ビタミン剤を服用してお昼動ける。
・無汗(入浴時、運動時も)。入浴後息切れ。
・寝つき1~3時間かかる、多夢。
【増悪因子】
肩こり~頭痛時、疲れすぎた時(月経前と月経後1週間に疲労感増悪)
【緩解因子】
肩こりに関して:1~2時間横になる、頭頂部の指圧。
【病因病理】
この患者さんは、様々なストレスがあっても中々発散することが苦手で内にこもってしまうタイプです。発散できないと、(肝)気の巡りが停滞してしまいます。
彼女の場合は、慢性肩こりが悪化してから発症していますので、肝気の停滞が体の上部に起こりやすい傾向にあります。地に足がついてないと感じるのもこのためです。
更に、悶々とした悩みが継続すると、脾胃に影響がでます。それは、食欲不振や便秘や軟便からも分かります。
脾胃は気血生化の源と言われているように、脾胃の弱りが継続すると栄養不良になり気血が不足し、貧血症状等が現れます。月経中の動悸や疲労感等からもわかります。
そして、血が不足すると、精神が不安定になったり、不眠になり易いです。不眠になると血を養えず更に不安感が増すという悪循環に陥ります。
月経中に発症するのは血虚(不足)のためで、月経前に発症しているのは、子宮に血が集まって髄海(脳)に血が不足するためと考えました。脈や舌、その他ツボにもそれらの反応が表われていました。
よって、証は、肝気上逆<心血虚証による意識障害として治療していきました。
【治療と経過】
1診目は打診を使用して、上に上がった気を下す治療をしました。2診目以降は、後渓を中心に、血を補いつつ上の気を下げ精神を安定するように治療していきました。
時々、配穴を三陰交に変えたり、脾兪を補ったりしていきました。
4診目ごろからよく眠れるようになってきました。強いストレスがかかると不眠になり、胃痛(空腹時痛は胃酸過多傾向→胃気逆)が生じます。
現在まで週1回の鍼治療を始めて2か月後の年末と春3月の2回倒れましたが、春は月経前でしたので、月経前には詰めて治療するようにすると、倒れなくなりました。
現在治療継続中です。経過は良好で多少のストレスがかかっても月経時でも倒れなくなりました。
【まとめ】
一過性の意識障害を東洋医学では「暈厥(うんけつ)」と言います。
『症状による中医診断と治療』では、「突然に意識が消失して四肢(手足)が冷え、一定時間の後に覚醒して、失語・顔面神経麻痺・半身不随などの後遺症を伴わないこと」とあります。
このような意識障害の症状には、鍼治療の効果大です。ただ、弁証分型も上記の著には6つ程挙げられており、多面的観察をしっかりして総合的に判断する必要があります。
また、その時点での証だけでなく、病因病理を把握して病の流れをつかむことが重要です。
実際この患者さんも、初めは虚>実を中心に治療していきましたが、治療過程で右内関というツボに熱を持って張ってきたり(沈んでいたツボが浮いてきたと考えます)、細脈が弦脈に変化したりしてきましたので、
治療戦略を変える(実>虚)必要があります。よって百会や督脈等実側のツボを時々使用しています。
身体からしっかり治療していけば多少のストレスにも強い心神になり根治できると考えます。
【主訴】不妊 39歳女性
【初診】平成27年2月
【現病歴】
結婚して4年後(平成26年)に初めて妊娠し、心音も確認できたものの約2ヶ月程で稽留流産により掻爬。流産後は、精神的ショックが大きかったが、約1ヶ月後に月経が再開し徐々に気分も回復する。
10年前から子宮筋腫3センチ大が数個あったが徐々に大きくなり数も倍増。不妊治療には抵抗があり、鍼で身体を整え妊娠したいとの事で来院される。
【その他の問診事項】
・20代ギックリ腰2回
・冬は月経周期が遅くなり、頻尿
・30歳すぎ~ほぼ毎朝両手指が浮腫み動かしにくい。
・30歳すぎ~疲労時やストレス時右耳鳴(高音)耳閉感。
・ストレスで寝付きが悪く多夢。
・運動しても足は冷える。
・月経前イライラ・過食・乳張・頭痛。月経後消失。
【各種弁証】
八網弁証:
裏 (表証所見なし)、
虚寒 (腎陽虚)
実 (肝鬱気滞証、衝脈気結証)
臓腑経絡弁証:
<肝鬱気滞>…月経痛、月経時の乳房脹痛、月経前のイライラ・肩こり・便秘、朝両手が浮腫み動かすと治る、ストレスで過食、ストレス時高音耳鳴り、
脈滑弦、重按+、右肝の相火、顔面肝抜け、合谷R実・L虚熱感あり、太衝L実・R虚中の実で熱感あり、後渓R虚中の実、両(右>左)肝兪実。
<腎陽虚>…足冷、冷えると頻尿、冬に月経が遅れる、経血薄く減、冷えると尿漏れ、温飲好み少量、長年の右耳閉感、腰痛、気海、太巨、両志室冷え、照海L虚、右尺位やや硬い脈、舌胖大歯根有、舌色あせ湿潤、顔面腎の白抜け。
<衝脈気結証>…子宮筋腫、少腹部の脹痛、冬月経後期、乳房脹痛、流産経験有、
太衝L実、R熱感、公孫L、三陰交R実、照海L虚、
【正邪弁証】
入浴後、二便後、運動(ヨガ90分)後、月経後に身体が疲れずスッキリする事や、気滞により様々な症状が出ていることから、全体的には実証と考えます。虚は、上記のように腎の陽虚所見が多く見られ、運動等、気滞がとれても冷えは除去されないことから、陽虚を意識しながら治療をすすめていく事にします。
【チャート図】
【病因病理】
七情不和(過剰ストレス)により肝気の昇発作用や疏泄作用が阻害され、気の巡りが悪くなり、肝鬱気滞から、血瘀(子宮筋腫)が形成されたと思われます。子宮筋腫等、下焦(下半身)に気が停滞しやすいのは、下焦の弱りと共に腎の陽気不足も重なったためと考えました。ストレスにより肥厚甘味の過食が継続すれば、脾を弱らせ、脾と腎が互いに補い合えなければ腎虚がすすみます。
また、生殖機能は衝脈が主っています。この衝脈に不足や不通が生じれば妊娠しにくくなります。患者さんは、肝経の気滞が衝脈に影響し、月経不順・痛経・乳張などが生じ、更に腎陽虚による陰寒の邪が不通を助長させ不妊に至ったものと考えました。
【治療方針と治療】衝脈解鬱・疏肝理気(衝脈は肝経と密接なので肝の疏泄作用を高める治療方針とします)
1診目:後渓(右)→右肝之相火緩む。
2診目:申脈(右)→右耳自閉感マシに。右鼻から血混じりのドロってした鼻水が出る。
3診目:後渓(左)→耳閉感消失。
5診目~8診目:三陰交
9診目~42診目:太衝 →27診目から8日間タール状の黒便が大量に出る。
42診目で妊娠陽性反応。
43診目~47診目:太白灸 →不正出血の為。
48診目(8週目)~88診目:後渓、申脈、太衝、照海のいずれか。(風寒時は外関)
【治療結果】
上記の通り、3診目には耳閉感が消失する等、鍼の効果が早くから現れました。当初はご自分の体調や不妊に関してかなり神経質に悩まれ、眉間にいつもしわを寄せておられましたが、治療するたびに明るくなって本来のご自分の性格に戻られました。
足も温まり腎陽虚が改善されてきたばかりでなく、27診目から黒い便が8日間ほど続き、瘀血が下ったようです。その後、すぐに妊娠されました。妊娠後も鮮血少量出血がありましたが、これはバックにあった脾の弱りからくる統血作用の低下と見立て太白の灸を施し改善されました。
また、大きな筋腫の為に定期的に大学病院で検査を受けられていましたが、59診目の検査では筋腫が壊死していたようです。
赤ちゃんも順調に育っており、後少しでご出産です。
患者さんは、赤ちゃんの姿の無い時から出産まで鍼治療を受けられ、本当に楽しい妊娠生活を送られていました。間もなくお母さんになられる彼女は、もうすっかり明るく逞しい女性に成長されました。鍼を信じて本当に頑張って通ってきて下さいました。心から感謝いたします。スタッフ共々可愛い赤ちゃんに会えるのが楽しみです。
【主訴】梅核気(喉の閉塞感)43歳女性
【初診】平成27年6月下旬
【現病歴】
約1年前の2月、喉のつまりと口渇が出現(この頃、毎年ご主人の転勤の辞令が決定する頃で過度に緊張している)。過去にも2回、同様の症状が出現する。痰(透明)がいつも喉にからみ、常時ゲップがでて口に苦みを感じる。嚥下には影響なし。
数か月後の春、食後に胸やけが伴うようになり、食欲減退。体重は4キロ減少する。ジョギング中にも吐き気がでるようになりジョギングを止める。
【増悪因子】
何もせず、ボーっとしている時。(過去2回の喉のつまり感は強ストレスから)
【緩解因子】
起床時、目標があって動こうとする時、忙しい時
【その他の問診事項】
・雨天前、頭痛。
・出産後月経痛減少。月経前イライラ、月経後体調は良、主訴は不変。
・足が冷え、冬はこたつから出られない。
・口の中にピリピリした痛み、場所は日によって変化、口内炎出来やすい
・幼少期、扁桃腺炎で高熱出し、小学校時両扁桃腺切除。
・40歳に副鼻腔炎発症。
・幼い頃から迷子になる夢をよく見る。
・目の充血。
・主訴発症前に萎縮性胃炎になる。
【各種弁証】
八綱弁証: 裏(表証所見なし)、実(肝気上逆証)、上熱下寒。
臓腑経絡弁証: 肝:月経前イライラ、春季に発症、顔面診肝白抜け、舌辺剥げ、舌尖紅、弦脈、太衝、肝兪、胆兪、合谷、肝之相火右等の反応。
【弁証】肝気上逆証
【チャート図】

【病因病理】
過去に2回ストレスから同症状が起こっていますが、今回は、ご主人が単身赴任から戻ってくると分かってからの発症です。毎年春に、ご主人の転勤の有無でハラハラされる等、緊張もピークになっていたところ、嬉しさで肝気が上ったものと思われます。日常の過食や不安感等から胃に負担をかけていたため、普通は下降する胃気が逆に上がり曖気(ゲップ)が止まらなくなっています。
また、鍼治療の予約を入れた時から症状がやや改善されていることからも、症状に対する安心感から肝気(緊張)が緩んだためと思われます。したがって、この喉の閉塞感は、七情に起因する肝の疏泄機能失調により、肝気が上焦(喉)で鬱滞したものと考えました。
【治療方針と治療】疏肝降気(肝気を巡らせて気を下げる)
初診から6診目:太衝
8診目から10診目:後渓
11診目から14診目:太衝
15診目から20診目:後渓
【治療結果】
5診目には当初10だった主訴は2に軽減されました。痩せたと言われる事に対するショックもあり、6診目には食べ放題に行かれていますが、主訴の悪化はありませんでした。不安感も無くなり20診で治療は終了しました。
東洋医学では、この喉の閉塞感は梅核気といって痰と気が喉で結びついて発症すると考えますが、肝の疏泄機能が正常に働けば痰も巡り散ります。今回は気>痰の梅核気と考え、肝気を中心に治療し功を奏しました。日常的に多く見られる疾患です。
また、増悪因子に、何もせずぼーっとしている時を挙げられていますが、じっとしているため気が廻らない事での悪化と共に、ご本人の真面目な性格からも何もしていない事への罪悪感が緊張に繋がっていると思います。
ご両親共に小さい頃から厳しいご家庭に育った方は、往々にしてこのようにダラダラしている自身に対して罪悪感を持ちやすい傾向にあります。夢も小さい頃から迷子になる夢をよく見られてることからも、根底には自信が無く、ご主人等頼る人が側にいないと精神的に不安感が増すのだと思います。
日常、運動等で発散しながら、少しずつ心身を解放し自信を持たれる事で、ご本人の真面目な性格が良さとなって発揮されると思います。
【主訴】卵巣嚢腫による不正出血と下腹部痛
【患者】40代 女性
【初診】平成27年3月
【現病歴】2年前、左下腹部激痛と不正出血が1か月続いたため、病院に行くと両卵巣に嚢腫が見つかる。鎮痛剤を1日3回服用するも緩解せず右卵巣を摘出。術後腹部の激痛は緩解したものの、術後から生理不順になる。(生理周期延長、出血量の増減、月経が10日以上続き貧血で動悸や立ちくらみが起こる等々)。
また、左下腹部痛(しくしくした重い痛み)が月経後から次の月経まで続き鎮痛剤を1~2回/日内服する。月の殆どは鎮痛剤を服用している状態にあり、医者から左の卵巣手術を勧められるが断り鍼灸院に来院される。
(月経状況)初潮時から生理痛有(1日目から2日目)。下腹部刺痛。血塊なし(手術前は血塊多)、生理前にイライラし、月経後落ち込む。月経後は貧血症状が出て疲れ横になりたい。月経前軟便、月経中普通便、月経後は兎糞状便(便秘薬を内服)。
【その他の症状】
・卵巣嚢腫摘出術後から、下肢が冷えやすい、重だるい腰痛、むくみ(顔>下肢)、のぼせ(夕方疲れた時と冬に多い)、考え事で不眠になる。
・不妊治療を試みるが卵子が出来ない。
【弁証】
脾不統血証・気滞血瘀証
【各種弁証】
八綱弁証;裏(表証所見なし)、虚(脾不統血)、実(気滞血瘀)
臓腑弁証;
脾不統血:不正出血が少量でダラダラ続く、薄い赤茶色、生理前軟便、月経後の脱力感と落ち込みや気分低迷。雨の日は体が重だるく腹脹し易い、帯下(水っぽく多量、臭い痒み無)、緊脈(初診時月経13日目)、胖大歯根有り、淡白舌、白二苔、両太白~公孫の虚(右>左)、右脾兪虚。
気血津液弁証;
気滞血瘀:月経前にイライラし月経後緩解、月経痛刺痛、血塊有り、ストレスで便秘。舌腹に数個の血腫有り、太衝、三陰交、肝兪反応有り、少腹急結(左)。
正邪弁証;
正気虚(ダラダラ続く不正出血、月経後横になりたい、運動で疲労感増、舌色褪せ、やや胖嫩、脈左2指押し切れる)
邪気実(入浴後や排便後に身体がすっきりする、月経前イライラ、脈力あり)
不正出血は正気の虚メインで、卵巣嚢腫は邪気実と考えるも、正気虚の状態から、邪気実の瀉法は慎重に考える。
【病因病理】
患者さんは、幼い頃から考え事で寝つきが悪く、環境変化で便秘する等神経質な性格だったようです。また中学生の頃から月経痛が酷く鎮痛剤を服用し続けていた為、胃がシクシク痛むことが多い上、肥厚甘味の食を好み、脾胃に常に負担をかけている状態でした。
脾胃が弱いところ、仕事でも人一倍頑張り肝気を高ぶらせる生活が続いたことで、月経痛が増悪し下焦に湿痰や瘀血が形成されたものと考えました。実母も子宮の病であったことからも下焦の弱りが似ていた可能性もあります。右子宮摘出後、腰痛やむくみ、冷え等が出現したことから下焦に負担をかけた可能性もあります。
不妊治療も試みられますが、採卵が出来なかった事からも、気血生化の脾胃が弱り、月経時の多量出血や瘀血等から血虚傾向になり、妊娠に必要な肝腎の陰血不足を招き、衝任(衝脈と任脈)を滋養できず不妊になったものと考えました。
以上の事から脾の統血作用が低下し不正出血が出現したものと思われます。
【治療方針】
益気健脾>疏肝理気(化瘀)
正邪弁証から、不正出血は正気の虚メインで、卵巣嚢腫は邪気実を考えましたが、正気の虚を先ず補い、邪気実は正気虚が改善に向かってから瀉法を加えて散らす方針とします。
【治療と結果】
1~5診目まで:公孫穴(虚側)
6~9診目まで:脾兪(虚側)
10診目 蠡溝
11診目~12診目まで 後渓
13診目:太白整えの灸11壮
14診目~19診目 後渓
20診目~26診目 太衝
27診目~後渓(現在も継続)
初診から脾の弱りを補う為に虚側の公孫と脾兪を補うと、ダラダラ続いていた不正出血が止まったため、補血と心神安定の目的で後渓を使いました。
途中、10診目の蠡溝(れいこう)は、左の子宮自体に熱感があり患部が痛んでいた為、肝経で子宮に繋がるツボで熱感を取りました。即効性がありました。
13診目の太白のお灸は、少し出血した後、疲労感があったため益気を目的に使用したものです。
脾の気(健脾)を補う治療で不正出血は殆ど止まりましたが、子宮のジクジクした痛みがあり鎮痛剤を服用されてました。治療を進めるうちに身体が軽くなり、15診目頃から殆ど鎮痛剤を使用しなくてもよくなり、月経も一週間で終わるようになり、仕事にも復帰されました。
まだ無理をした時は腹部が重くなったり、月経痛も出現しますので治療継続中ですが、月の殆ど鎮痛剤漬けの生活から、殆ど鎮痛剤を使わなくても良くなり鍼の効果を実感して頂いています。
肝、脾、腎と言えば最も肝腎要の臓です。この三者が身体の中で連携して健康を維持していると言ってもいい程です。
患者さんはこの三者のバランスを大きく崩して病が発症しましたが、常にこのバランスを調整しておけばお母さんと同じ病に倒れる事はありません。
この未病治が東洋医学の凄いところでもあります。
【主訴】動悸
(その他の随伴症状)過呼吸、手足のしびれ、めまい。
【初診】平成27年7月下旬、39歳 女性。
【現病歴】30代前半、第一子出産直後に1回目の発作、突然の動悸、手足のしびれ、揺れる様なめまいが現れる。出産前の5か月間大きなストレスがあり睡眠不足が続いていた。抗不安薬で上記の発作症状は消え、その後8年間発作は出現しなかったものの、
第二子、第三子を出産し、育児、家事、仕事で多忙な中、2回目のひどい発作が出現する。動悸、過呼吸に加え、頭痛も出現し救急搬送される。ここから毎晩寝入りばなに動悸がして不安と緊張が増すようになる。
【増悪因子】
寝入りばな、乗り物等閉塞された環境、生理前、疲労時。
【緩解因子】
運動、集中時、食事量減らす。
【その他の問診】
・小さい頃よく行事前発熱していた。
・胃もたれ。
・下肢のむくみ。
・第一子出産後から生理痛が消失。
・妊娠時(三人共)貧血診断受ける。
・月経後身体は楽になる。(主訴に変化なし)
【弁証】心肝気鬱>血虚証。
【各種弁証】
八綱弁証:
裏(表証所見なし)
虚(血虚)
実(心肝気鬱)
臓腑弁証:
(心肝気鬱)
・肝気鬱:イライラ、月経後身体楽になる、喉が詰まる、(体表所見)顔面肝色抜け、両舌辺剥げ、左関上枯弦脈、太衝・肝兪の反応)
・心気鬱(閉塞された所や緊張で呼吸困難、動悸、不安感(体表所見)顔面心部位色抜け、舌尖紅刺、両心兪反応、後谿の反応、心下~脾募の邪)
気血弁証:
・血虚:貧血、爪が割れ易い、月経過少、舌質色あせ、光が眩しい、心兪、脾兪、太衝等の虚の反応等。
正邪弁証:
夜になると疲れてくる事や、脈幅も無い事からも正気の虚はあるものの、入浴後、生理後、運動後等に身体がすっきりする、動悸、過呼吸は運動後に変化しない事等から邪実が中心と考えます。ただ、血虚の所見が顕著に見られることや、寝入りばなに動悸が打ち、不安感が増すことから、バックには心血不足があり、血不足により気鬱が更に増すと考えました。(陰陽に分けると、気は陽で血は陰になり、血が減ると相対的に気が勝ち気血の陰陽バランスが乱れます。)
よって、心血を補いつつ気鬱を緩解するように治療をしていくことにしました。
【病院病理】
患者さんは、三人小さいお子さんを育てながら仕事もこなすという超ハードな生活を送られていました。その上 第一子出産前に寝不足が続き、出産後に身内を亡くされるという大きなストレスがありました。肝鬱気滞から、寝不足と心神に大きなショックを与えたことから心肝気鬱となり、動悸、不安感等の症状が発症したものと考えました。
【治療方針】
心肝解鬱
1診目~15診目まで:後谿穴 (2診目のみ申脈)
【治療結果】
1診目後から動悸は10→1~2に激減。3診目には動悸が気にならなくなり、電車の中などの緊張時も寝入りばなにも動悸は起こらなくなる。胃もたれや足の浮腫みも余程不摂生をしない限り解消された。
【考察】
現在も治療継続中ですが短期間でお元気になられました。この後渓のツボの効能がこの患者さんの証(今の時点での身体の状態を東洋医学的に一言で表現したもの)にピタリと一致したからだと思います。(心肝気鬱証<血虚証)
このツボは北辰会代表の藤本蓮風氏が半世紀にわたる臨床を積み重ねる中で、見出された重要穴です。同じ後渓でもそのバリエーションは様々ですので、この証のみに使用するツボではありません。(藤本蓮風著『経穴解説』参照)
またこの動悸は、緊張状態が続いて発症したものです。その緊張状態が少しの緩みもなくマックスに達した時、過呼吸を伴い救急搬送になっています。
更に、寝入りばなの動悸は、ホッとして意識する事なく気が緩んだ状態の時の発症と考えました。それは、この動悸は反対に気が張っていると、ある程度は抑えられるという事でもあります。実際そのようでした。
そこで、血虚の度合いはさほど酷くなく、抑え込んでいる気鬱のレベルが酷いと考えました。ただ、この患者さんの場合は、気鬱を解く事を中心に瀉法(気鬱を除くために邪をたたく事)をするより、少し血を補いつつ、心肝の気鬱も同時に緩解するという方法がいいと思い後渓を使用しました。これは功を奏したと言えます。
鍼の効果はこのように本当にシャープです。弁証を間違えず患者さんに安心感を持ってもらってこそ効果も倍増すると日々の臨床の中で改めて感じた症例です。